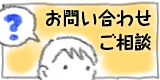社労士から一言~「扶養親族」と「被扶養者」の違いについて~

早いものでもう12月、給与担当の皆さんは年末調整に向けて準備を進めていらっしゃることと思います。
年末調整の際の大切な作業が、控除対象配偶者と共に扶養親族の有無を確認することです。
さらに来年の給与計算の際には扶養親族の取り扱いが変更されることもあり、生年月日の確認等、注意が必要です。
ところで皆さんは「扶養親族」と、健康保険でいう「被扶養者」の違いをご存じでしょうか。
年末調整や来年の給与計算の際にカウントすべき扶養親族の取り扱いについては、税理士さんにご確認いただくとして、今回はよく混同される健康保険法上の「被扶養者」について、所得税法上の扶養親族との違いを中心に確認していきましょう。
そもそも「親族」とは民法に規定される6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
所得税の計算においては扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等及び同居特別障害者である扶養親族に該当しているかどうかを、所得者と生計を一にしているか、合計所得金額、年齢等の要件を満たしているか等、その年の12月31日の現況により判定することになっています。
一方、健康保険でいう「被扶養者」は次のように定められています。
1.被保険者に主として生計を維持される直系尊属、配偶者、子、孫(曾孫は含まない)及び弟妹(兄姉は含まない)
2.被保険者に主として生計を維持され、かつ同一世帯に属する
①被保険者の3親等内の親族、
②被保険者と事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子、
③前記②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である者は、被扶養者には含まれません。
ここでいう「主として生計を維持」とは被保険者に生計を依存し、その生計の基礎を被保険者に置くという意味であり、具体的には被扶養者の年間収入が130万円 (60歳以上または障害者の場合は180万円)未満かつ被保険者の年収の1/2未満(同一世帯に属さない場合は130万円または180万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない)かどうかで判断されます。
ただし、この認定基準は画一的なものではなく、実務上は130万円(180万円)未満という要件さえ満たせば、保険者の判断により弾力的に運用されているようです。
収入は、被扶養者の認定申請時点から1年以上続くとみなした見込み年収で判断されるため、仕事を辞めた配偶者がそれまで130万円以上の給与を得ていたとしても、退職日以後無職であれば収入要件を満たすことになります。
注意していただきたいのは、認定基準額は「所得」ではなく「収入」で判断されるということであり、この収入には非課税の遺族年金や障害年金、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も含まれるという点です。
遺族年金を受給されている老親を被扶養者にしたいときや、仕事を辞めた妻が基本手当を受給し始めた時など、特に注意が必要です。
基本手当については、総受給額が130万円未満であったとしても、基本手当の日額が130万円÷360日分(3,612円)以上であれば収入要件を満たさないこととなり、受給終了後に改めて収入要件を満たすかどうか判断することになります。
また夫婦共働きの場合は、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して判定を行うとされており、必ずしも収入の多い方が被扶養者になれないということではありません。
「同一世帯」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるかどうかや、被保険者が世帯主である必要はありません。
入院等で一時的に別居している場合で入院等の前に同一世帯であった場合には、同一世帯の要件を満たすとされています。
また、「控除対象配偶者」は戸籍上の配偶者に限られますが「被扶養者」の範囲にはいわゆる内縁関係にある配偶者も含まれます。
ただし、生計維持要件のみで認定される「子」は実子と養子に限られ、養子縁組をしていない配偶者の連れ子(継子)を被扶養者にするためには同一世帯に属していることが必要です(上記2.の要件)。
また内縁関係の配偶者の祖父母・孫・兄弟姉妹は3親等内の親族には含まれません。
従業員さんから被扶養者の手続き申し出があった時には、所得税法の「扶養親族」と混同されている方もおられますので、必要な添付書類をよく確認し、要件を満たしているかどうか不明な点は健保協会に確認して下さい(特にパート勤めの配偶者など)。
なお、国民健康保険には被扶養者という概念はありません。
健康保険組合や国保組合に加入されている事業所では、各組合ごとに認定要件や添付書類が違っている場合がありますので確認が必要です。
(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)